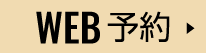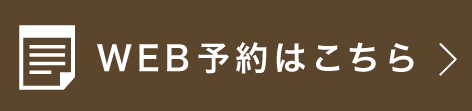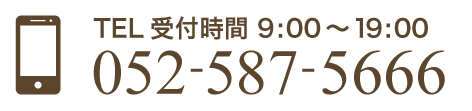- とわたり内科・心療内科 TOP>
- 診療科 / 心療内科・精神科>
- ASD(自閉スペクトラム症)
ASD(自閉スペクトラム症)
ASD(自閉スペクトラム症)とは
自閉スペクトラム症(ASD)は、発達障害の一種であり、社会的なコミュニケーションの困難さや特定の行動に対する強いこだわりなど、多様な特性が見られます。
幼少期から周りとのコミュニケーションがうまく行かずちょっとした違和感を感じてはいたものが,大人になり社会生活を営む中でそれらがよりはっきりとしたものになり,仕事やプライベートで問題が生じて,診断に至るケースが増えています。

ASDの症状は?
■コミュニケーションの問題
・冗談が通じない
・言葉を額面通りに受け取ってしまう
・表情や身振りから相手を理解することができない
・人の気持ちを察することができない
・距離感が近い
■独自のこだわりが強く、臨機応変に対応出来ない
・同じ習慣へのこだわりが強い
・独自のルールが多い
・急な変化に対応できない
・融通が利かない
・生活パターンが変えられない
・興味や関心が偏っている
■感覚が敏感になる(聴覚過敏,触覚過敏など)
・周囲の人は気にならないような些細な音が気になる
・クラクションの音で「パニック」になる
・洋服のタグが体に触れるのが不快でタグを取り外す
ASDの原因
ASDの原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な要素や環境的な要素が関係していると考えられています。
生まれつき、脳の中枢神経系という情報を整理するメカニズムに特性があるため、できることとできないことにばらつきがあります。
あくまで個人の特性であるため、病気として治療することが難しい側面もあります。
個人の特性を詳しく知りたい場合は、AQテスト(簡易検査)やWAIS・WISCなどの知能検査(複雑心理検査)で、能力や特性を把握できます。
当院でも行っておりますので,ご相談ください
ASDの診断
自閉症スペクトラムは現在の国際的診断基準では広汎性発達障害とほぼ同義語として使用されており、自閉症、アスペルガー症候群と言われていた病名も包含されています。
おもに、
・社会的コミュニケーションおよび対人関係の障害
・常同性の障害(行動・興味に限定されたこだわり)
が重要な診断基準となっています。
具体的には以下のA,B,C,Dを満たしていることとされています。
A:社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害 (以下の3点で示される)
- 社会的・情緒的な相互関係の障害
- 他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)の障害
- 年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害
B:限定された反復する様式の行動、興味、活動(以下の2点以上の特徴で示される)
- 常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方
- 同一性へのこだわり、日常動作への融通の効かない執着、言語・非言語上の儀式的な行動パターン
- 集中度・焦点づけが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある
- 感覚入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する環境に対する普通以上の関心
C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある
D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている

ASDの治療
ASD自体は「病気」というより本人の「特性」であるため,薬で治療することは難しい側面があります。
実際にADHDと違って症状を改善させる有効な薬物療法も今のところ存在しません。
ただし、大人のASDの方は、ADHD、うつ病、不安障害などを合併し、症状を複雑化・重症化し社会生活に多大な支障を生じていることも多く、これらの合併症に対する適切な薬物療法は有用です。
ASDの方に提案できる治療法は環境調整やカウンセリングがメインとなります。
環境調整とは、ASDの方と周囲の人が、自閉スペクトラムの症状や特性をよく理解したうえで、生活面において工夫をおこない、本人が過ごしやすい環境を整えることです。
主治医による診療や臨床心理士との心理カウンセリングをもとに、家族や職場の人達にも協力してもらうことが必要となります。
当院では、病気の理解と対処スキルの向上のために、個別心理カウンセリングは重要な治療法と位置づけています。
また、集団による気づきやコミュニケーションスキルの習得を目的とした集団療法も重要な治療機会と捉え、「大人の発達障害のための集団認知行動療法」(G-CBT)や休職中の方にはリワークプログラム(復職支援プログラム)を提供しております。
自閉スペクトラム症(ASD)は治らないので治療方法はないと諦めずに、主治医・臨床心理士らと信頼関係を築きながら一つ一つ困難を克服することにより、生きづらさの改善と自己効力感の回復に繋げていきましょう。
ASDのQ&A
近年、自閉スペクトラム症の人は約100人に1人いると報告されています。
男性に多く、女性の約4倍の発生頻度です。
ただし女性では困難を自分で抱え込み,社会的困難の現れが目立たず、過少評価されている可能性もあります。
■その他 取り扱っている疾患
うつ病 躁うつ病(双極性障害) 適応障害 大人の発達障害 ADHD(注意欠如多動性障害) ASD(自閉スペクトラム症) パニック障害 不安障害 強迫性障害 不眠症 心身症 更年期障害 男性更年期障害(LOH症候群) 自律神経失調症 めまい症 慢性疲労症候群 線維筋痛症 新型コロナウィルス感染症後遺症外来> 診療案内に戻る