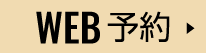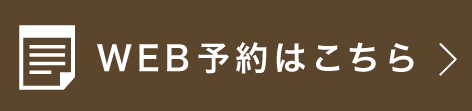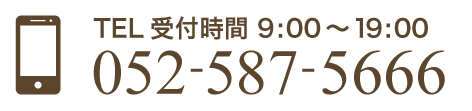- とわたり内科・心療内科 TOP>
- 診療科 / 心療内科・精神科>
- 適応障害
適応障害
適応障害とは?
適応障害は、環境の変化など強いストレス因子によって、心身に不調を来し、日常生活に支障を来す病気です
誰にでも起こりうる心の病気であり、はっきりとしたストレス因子があり、それが取り除かれれば多くは症状が改善されます。
ただしストレスが長期間続くと、うつ病などにも発展していくことがあり、早期の治療介入が必要となります。

適応障害の原因
適応障害は先に述べたように強いストレスが原因となり発症します。
ストレス要因にはさまざまなものがあり、まわりから見ると一見ストレスと感じられないようなことも、本人の性質と一致しない場合は強いストレス要因となることがあります。
- 職場でのストレス:異動、昇進、多忙、重責、パワハラなど
- 学校でのストレス:受験、進学、転校、いじめ、など
- 家庭でのストレス:結婚、離婚、出産、育児、金銭問題、など
このように日常生活の様々な出来事がストレス要因となり、誰にでも起こりうる病気であることに注意しなければなりません。
適応障害の症状
心身両面で様々な症状が起こり得ます。
■心理面の症状
- 憂鬱
- 不安
- やる気が起こらない
- イライラする
など
■身体面の症状
- 不眠
- 倦怠感
- 吐き気
- 動悸
- 頭痛
- 涙が溢れてくる
適応障害の診断基準
上で述べたような症状はこれまでにみなさんも一度は経験したことがあるかもしれません。
ではどういった場合に適応障害と診断されるのでしょうか?
国際的な診断基準(DSM-5)をご紹介します。
- 明確なストレス因子に反応しており、そのストレスが始まってから3ヶ月以内に症状が発症している
- 下記のうち、いずれかがあてはまる
・ストレスが原因となりあらわれている症状が一般的に予想されるよりも強い
・社会的、職業的な状況において支障が出ている - 他の精神疾患では説明がつかない
- その症状は死別反応ではない
- ストレスの原因がなくなると、症状がその後6ヶ月以上継続することがない
以上のように5つの項目を満たす場合に適応障害と診断されます。
明確なストレス要因があること、またストレスの原因が取り除かれると、比較的速やかに改善することが特徴です。
日常生活を送る中で誰しも大小様々なストレスを抱えていますが、これによって日常生活に大きな支障が出ている状態です。

適応障害の治療
適応障害の治療は、医師との話し合いを通しながら原因を明らかにし、個人個人に最適な治療法を探していきます。
ストレスは、1人で我慢し抱え込むと、余計に悪化するスパイラルに陥ります。
1人で抱え込まずにまずは相談をして下さい。
■ストレス要因を取り除く(環境調整)
適応障害は明確なストレス要因があることが特徴のひとつであり、それを取り除くもしくは軽くすることが治療の根幹になります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 残業時間が多い → 担当業務の変更や仕事量の調整を会社と相談する
- 職場の雰囲気が合わない → 異動を相談する
- 人間関係に悩んでいる → 相手と少し距離を置いてみる
- 家事・子育てが負担 → 家族と役割の分担をする
- 身体が疲れすぎて朝起きれない → 休職をする
このようにまずは少しでもストレスが少なくなるように環境を調整する必要があります。
特にストレスの原因は職場にある場合が多く、一定期間休職をすることで、身体面のみならず精神面での回復も期待できます。
責任感が強く休職するのに抵抗感があり、頑張りすぎてしまう方も中にはいますが、それが続くとどこかで破綻してしまいうつ病などのより深刻な状態に至る可能性があります。
そうなる前に適切な環境調整を行うことが重要です。
■薬物治療
また症状が深刻な場合は薬を用いる場合もあります。憂鬱でなにもやる気が起きない、ふとした時に涙が出てしまうなど抑うつ症状が強い場合は抗うつ薬を、不安や緊張が強い場合は抗不安薬を、不眠などの身体的な症状がある場合は睡眠薬などを、症状に合わせて用います。
ただし適応障害はストレス要因が取り除かれると症状は軽快することが多く、長期投与ではなく細やかな内服の調整が必要となります。
■精神療法
ストレスを取り除くことだけでなく、ストレスにうまく対処していく術を身につけることは、再発を防ぐ意味でも大きな効果があります。
物事のとらえ方(認知)や行動のパターンを、順序立てて、段階的に分析し、より現在の状況に適した考え方や行動のパターンに変容させていく治療法として認知行動療法があり、臨床心理士(カウンセラー)と一緒に取り組んでいきます。
当院では経験豊富なカウンセラーが多数在籍しております。
適応障害 Q&A
うつ病と適応障害は、いずれも発症にストレスが関与している精神疾患ですが、うつ病は脳内神経伝達物質が低下してしまった状態でストレス要因を取り除いてもすぐには改善しません。
一方、適応障害はストレス要因を取り除くことですみやかに症状の改善が期待出来ます。
ただし、はじめは適応障害であったものが、長期間の強度のストレス負荷によりうつ病に至ることはよくあるため、早期の診断介入が必要です。
一般的に症状が改善するまで休職をおすすめします。
復職する際も、いきなり元通りに勤務を再開するのではなく、まずは午前のみからなど段階的に復職していくことが望ましいです。
休職が必要がどうかも含め、まずは受診の上、ご相談ください。
休職をして休息をとる場合は、とにかく身体を休めることが大切です。
「気分転換に出かけよう」と考える方もいるかもしれませんが、事前に計画を立てたり、遠くまで足を運んだりすることが、かえって負担になり悪化する場合もあります。休職中はしっかりと休むことに専念しましょう。
■その他 取り扱っている疾患
うつ病 躁うつ病(双極性障害) 適応障害 大人の発達障害 ADHD(注意欠如多動性障害) ASD(自閉スペクトラム症) パニック障害 不安障害 強迫性障害 不眠症 心身症 更年期障害 男性更年期障害(LOH症候群) 自律神経失調症 めまい症 慢性疲労症候群 線維筋痛症 新型コロナウィルス感染症後遺症外来> 診療案内に戻る